
日本酒の明日を語る
複雑な発酵によって生まれる「うまみ」、そして今求められる多様性
酒の産業を知る - 酒文化論・技術論
「醸造」は、日本独自の言葉であり日本特有の文化です。なかでも日本酒は、複雑な発酵によって生まれる「うまみ」が最大の特徴です。その味わいは古くから自然風土の中で育まれ、酒の嗜好も螺旋階段を上がるように進化してきました。これからは、「米のうまみ」を生かした「さわやかな風味」の酒を造ることもひとつのポイントになるでしょう。
語り手:栗山一秀。1926年生まれ、月桂冠元副社長。
出典:『酒類・食品ニュース&解説』2190号~2193号、日刊経済通信社(1999年)に掲載されたインタビューより構成
酒のうまみ、日本酒の味の原点
「うまみ」というのは、東アジアの食品に共通した味の底流になっています。タンパク質やアミノ酸は、人々にとって重要な栄養源であり、その存在を示す信号が「うまみ」といわれるぐらい大切なものです。東アジアでは、発酵によってできる複合体の「うまみ」を、「醤(ジャン・ひしお)」と総称してきました。コメを主食とし、副食が野菜主体という東アジアの食事にあっては、どうしても必要な食品であり、万能調味料でもありました。狩猟民には、鳥肉や獣肉を発酵させた「肉醤(ししびしお)」があり、農耕民では醤油や味噌のような「穀醤(こくびしお)」や「豆醤(まめびしお)があり、漁民では「魚醤(ギョショウ・うおびしお)」や「塩辛」が造られてきました。私たちはそれらをいろいろな食品とともに食べてきました。
「醤」の本体は、発酵によってできる複雑なアミノ酸の複合体です。明治以後発見された「昆布の味」の成分グルタミン酸ソーダも、鰹節(かつおぶし)の成分のイノシン酸ソーダも、シイタケの味のグアニル酸ソーダもみな日本人が好きなものを追究した結果、開発に行きついた「うまみ」商品だといえます。
日本酒も麹菌による複雑な発酵によってできる「うまみ」が味の原点になっているのです。私は数年前から国立民族学博物館の共同研究員の一人として『論集 酒と飲酒の文化』(1998年、平凡社発行)を研究するなかで、「日本酒の特質とは何か」について考察してきました。「日本酒のうまみ」は、東アジア特有の複合醗酵によってできるアミノ酸と多くの酸が主体となっています。
同じ醸造酒のビール、ワインと比べてみると、そのアミノ酸含有率はビール「1」に対し、ワインは「3」、日本酒は「8」とケタはずれに多い。しかもアミノ酸というのは、その種類が変わると、AからBに移行するのではなく、予想もしないZまで飛んでいってしまい、まったく別の味になるところに発酵の怖いところがあり、面白いところもあります。

「醸造」(じょうぞう)こそ日本独自の文化
面白いことといえば、欧米には「うまみ」という味覚を表す言葉がありません。このことからもわかるとおり、欧米には昔から「うまみ」に関連した文化は発達しなかったようです。現在、日本語の「UMAMI」という表現が国際的に通用する言葉として世界で使われています。
さらにこのような複雑な発酵を包括した言葉として「醸造」という概念を生み出したのも日本人です。「醸造」という言葉は、日本では千年も前の「延喜式(えんぎしき)」に記録されているほど古い言葉ですが、これも英訳しようとすると該当する言葉がありません。「brewery(ブルワリー)」では、ビール醸造の意味しかありません。日本酒をはじめ味噌、醤油、納豆などを作ることを表す「醸造」こそ、外国語に翻訳できないまったく日本独自の言葉であり、日本特有の文化を表しているといえます。 複雑な発酵によって生まれる「うまみ」は、今も日本酒に厳として存在し、大きな特徴となっています。
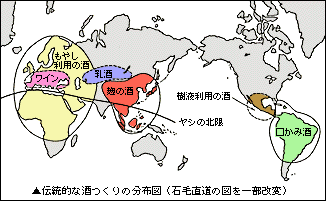
不易と流行、時代ごとに最高の技術駆使
日本酒は「国酒」として伝統を持った酒だと言われてきました。しかし、この言葉を皮相的・表面的に受け取るのでなく、本当にそうなのかを明確にすべきです。それにはまず、東アジアのいろいろな酒の共通点を調べ上げ、そのうえで日本酒の本質とは何なのかを考えてみる必要があると思うのです。日本の酒造りが次第に進歩・発展していく過程において、一方で日本人の優れた味覚とデリケートな感性が形成されていったと思われます。しかし、その根底には、いつの時代にも不易なもののひとつとして日本酒の「うまみ」があったといえます。
したたかな遺伝子の存在
これまでも日本人の食事のスタイルや内容、その嗜好などは時代とともにずいぶんと変わってきました。さらに将来、その変化はもっと激しくなると思われます。しかし、我々の嗜好を決めている遺伝子は不易なはずです。
現在の我々は、縄文人と弥生人の両方の遺伝子を持っています。その証拠に、日本人のうち約6割の人は縄文人の血(遺伝子)が濃く、酒が強い。これに対して、約4割が弥生人の血が濃いため、酒に弱い。さらに全く飲めない人も約4%います。我々はお互いにそういういろいろな遺伝子をしたたかに持ちつづけており、簡単には消えません。
青森県の三内丸山遺跡の調査で、縄文人はすでに栗の木を栽培し、その木材を建築用として使うとともに、栗の実も常食としていたことが明らかになっています。今の我々の焼き栗に対する嗜好は縄文人と同じかもしれません。日本は海岸から後ろを向いたらすぐ山で、川は滝になって落ちている。こんな地形があるからこそ、とれとれの海の幸、山の幸を食べ、新鮮さを喜ぶ日本人の嗜好が生まれたと思います。ただし、こうした不易な嗜好があるといっても、嗜好は、常にらせん状にレベルアップしながら変化し、進化し続ける面も持っていて、決して元には戻りません。その証拠に「昔の酒はうまかった」という人がよくいますが、当時の酒をそのまま再現したら、とてもまずくて飲めたものではないことをいやというほど知るはずです。 こうしたことをしっかりと認識したうえで、酒の嗜好や味覚の「不易流行」を考えていかなければならないと思っています。
原料米と造りの関係、ワインとの根本的なちがい
日本の酒造りでは、原料米はやはり重要です。山田錦という米は、いい酒を造りやすいからいい米なのです。ただ、最近の目をみはるような醸造技術の進歩によって山田錦と一般米との差は相当カバーされるようになってきました。その一方で、技術が進歩し、精緻化するほど同一品種の米でも産地の違いによる差異が逆にクローズアップされてきています。しかし、ワインにはヴィンテージがあるのに、同じ醸造酒でありながら日本酒にはヴィンテージがありません。どちらも農産物を原料にしている点では同じです。それについて多くの人が疑問を持っているのではないかと思います。
ワインの場合は、原料ブドウの品質は夏の天候が大きく影響します。秋の醸造段階で工夫し努力しても、不作の年は良いワインにはならないといわれます。実際、ブドウは摘み取った時点から果皮に付着していた酵母によって、すぐにも発酵が始まってしまうので手の打ちようがないといわれるほどです。浅井昭吾氏(元メルシャン山梨工場長)は「ワインはブドウの持っているポテンシャルをいかに引き出すかが醸造技術のすべてだ」とさえいわれています。

複雑な造りの工程こそ生命線
一方、日本酒はどうか。不作のとき、米の硬いとき、柔らかいときはどうすればよいかについて対応する技術が開発されてきました。それは、日本酒は造りの工程が極めて複雑であるため、各工程の技術によって随分とカバーされてきたからなのです。まず精白をどの程度にするか、いかに精米による割れを少なくするかなどが大きなポイントです。いうならば、日本酒の場合は原料米を精白する時点で農業とは縁を切ってしまうわけです。ついで、浸漬や蒸しの工程についての技術の違いも多く、どのような技術を採用するかによって以後の工程は相当違ってきます。さらには麹をどういう風に造るべきかということも大きな選択肢になります。各工程での技術の適否が、以後の発酵に関わる麹菌や酵母という微生物の活動に大きな影響を及ぼし、ひいては酒の良し悪しを左右することになります。さらにいえば、麹造りやもろみ発酵の段階で、微生物の働き如何によっては、その米が本来持っていないポテンシャルまで引き出すこともありうるわけです。
たとえば吟醸酒の場合、あの果物のような香りは米が本来持っている香りではなく、酵母が造る香りなのです。米を4割以上磨いて白くし、種麹はちょっとしか播かずにわざと生えにくくしたり、酵母にとってきびしい条件となる低温発酵までやるという、きわめて特殊な条件を設定して吟醸酒を造っているのです。なぜ、そうするのか。これまではその理由もわからず、多くの人の経験の積み重ねだけでやってきたのですが、最近の当社の研究によって、「吟醸香を出す酵素は低温でないと働かない」など、吟醸酒造りの条件も次々と解明され実証されてきました。
たしかに現在は、昔に比べると米の持っているうまみ成分を相当削り取ってしまったものを原料として発酵させています。ただ、もともと米はビール原料の麦に比べ、タンパク質の比率が高い。それだけに、もっと本来の「米のうまみ」を生かし、なおかつ「さわやかな風味」を造る方法を、じっくりとこれから考えていきたいものです。
 ▲左から玄米、精米歩合70パーセントの白米、50パーセントの白米
▲左から玄米、精米歩合70パーセントの白米、50パーセントの白米
低アル清酒の開発、アルコールに代わる「柱」を模索
「低アルコール清酒」について、我々個々のメーカーも日本酒造組合中央会(業界の中央団体)も長年にわたって試行錯誤を繰り返してきましたが、いまだに確実な答えが出ていません。確かに社会からの要望も強く、うまくやれば大ヒットするのですが、ひじょうに難しい課題です。
何百もある清酒のうまみ成分の分子は、それぞれがアルコール分子と手をつなぎ、アルコールが中心となって風味のバランスが保たれています。問題は、中心であるアルコール分が少なくなってしまうと、このアルコールに代わって柱となるべきものがいまだに見つからないことです。酒の風味全体のバランスが崩れ、よい商品になりません。
ビールの場合、アルコール分は低いのですが、ホップの苦味と炭酸ガスの爽快味という二本柱があるため、風味のバランスがとれているのだと思います。
アルコールの力はすごいもので、それ自体は無味・無臭でありながら、いつもうまみ成分のど真ん中にいて、親分として君臨している。アルコール分12%くらいまでなら、うまみの親分としての力もどうにか保たれるのですが、それ以下になると、子分のうまみ成分たちが勝手に活躍しだして統制がとれなくなるようです。
アルコールに代わる別の柱を探しながら、まずは10%~8%ぐらいの「低アルコール清酒」の開発に挑戦していかなければと思っています。
今から35年ほど前、ある座談会で「低アルコール清酒は必要か」が話題になったとき、私は「たとえ難しくても造ってみるべきだ」と主張したことを覚えています。その席で私がまだいちばん若い技術者だっただけに、否定論だった灘のI先生からは「できもせんことをいうな」と叱られました。当時から私は「低アルコール清酒」の開発については積極的肯定論者で、推進派でした。当時、いつも酒に白湯を入れ、倍に薄めた酒をふうふうしながら飲む先輩がいたので、私も真似してやってみると、これが結構いける。「熱さ」という外部条件が味覚の柱になってくれていたのです。「ははん、酒の燗というのは味の薄さを感じさせない効用もあるのだ」と、そのとき初めて知りました。これなどもひとつのヒントになると思います。
また、日本酒の本質である「うまみ」が薄まらないよう、とくに味覚に敏感な日本人に、しっかりと感じられるような「うまみ」を重視した酒を造ることもひとつのポイントになるでしょう。これからもいろいろなアイデアを出し合って、試行錯誤をどんどん続けていくべきだと思います。
- 【参考文献】
-
- 石毛直道・編(1998)『論集 酒と飲酒の文化』平凡社
※世界中の酒造りと飲酒文化について16人の研究者が共同研究を行った論考集
- 石毛直道・編(1998)『論集 酒と飲酒の文化』平凡社



