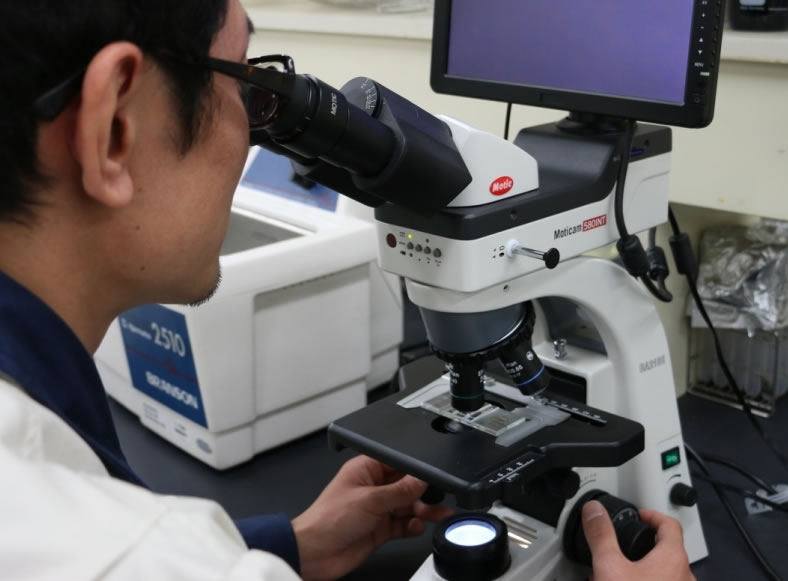
科学・技術の進歩と酒文化
伝統は常につくりあげ、そして変えていくもの
酒の産業を知る - 酒文化論・技術論
酒の専門紙に、吉田集而氏(国立民族学博物館教授、文化人類学)、浅井昭吾氏(ワインコンサルタント、エッセイスト)の対談が掲載された。その論旨に対して、おいしく飲むために、最新の科学・技術の活用が必要なこと、技術の活用によって市場が望む酒質をいつでもつくりうる体制ができた点など、私の考えを述べた。
語り手:栗山一秀。1926年生まれ、月桂冠元副社長。
出典:『フードロビー』大阪25周年記念号、日本食品工業倶楽部(1999年4月1日)より抜粋
対談「酒と人間との関わり」の反響
最近、酒類業界でも遺伝子工学の発展を中心とした科学・技術の進展は誠にめざましいものがある。 このような状況のもと、これまで「文化の酒」(注1)といわれてきたものが、果たして「文明の酒」(注2)として再生を果たしていけるであろうかという命題が、にわかに議論されるようになってきた。
注1:「文化の酒」、注2:「文明の酒」
「文化」とは、一つの地域や集団で習得され、そこで継続されてきた固有の生活習慣、しきたりや儀礼、行事などである。「文明」とは、地域に限らない普遍的な原理で、人が作った制度や法的規制などである。これらのことは、栗山一秀「酒と文化」にくわしい。
そんななか、『酒販ニュース』(醸造産業新聞社、1999.1.1号と1.21号)の紙上に、吉田集而(国立民族学博物館・地域研究企画交流センター教授、文化人類学)、浅井昭吾(ワインコンサルタント、エッセイスト)両氏による対談「酒と人間との関わり」が掲載され、かなりの反響を呼んだようである。
両氏とは、「酒文化」研究に関する先達として以前から親しくさせて頂いており、最近では、国立民族学博物館(以下民博)での2つの研究「酒と飲酒の文化」と「酒をめぐる地域間比較」の共同研究者でもある。したがって、両氏の持論や考え方はある程度理解していたつもりであった。 しかし、今回の対談における両氏の論には、私も少々承服しかねるところが散見された。それを要約すると、次の3点になる。
吉田集而氏と浅井昭吾氏の論旨
(1)日本酒は、明治以降、自然科学を導入し、米を磨き、酵母を選択し、温度調節を行い、どんどんピュアなかたちでコントロールしやすいようにして、一直線に大吟醸まできた。 こうした技術革新によって、昔は繰り返していたような失敗はなくなり、平均的なレベルで「まずい酒」はなくなった。しかし、これによって、昔あった「おいしい酒」が、よりおいしくなったとはいえない。
(2)科学的な合理性を追求した技術にによって生まれるものには、必ずしも「感銘の深さ」はない。かつては「自然の微生物の森」の中でつくられてきたものが、いまや、「純林のような環境」のもとでつくられている。酒の生命ともいえる複雑さをこうして単純化したため、「多様性」まで失ってしまった。
(3)清酒における米の精白、蒸留酒における連続式蒸留機での精留、清酒やウォッカを仕上げる際の炭ろ過、さらに、完成された四季醸造技術など、そのいずれもが酒の産地特性を失う「風土ばなれ」の技術であり、これらを多用することによって、酒はひたすら文明化の道を進むことになり、「文化の酒」としての復権はあり得ない。 こうした論旨に対して、私なりに気がついた点から逐一述べることとしたい。
昔の酒はよかったか?
(1)酒つくりに失敗がなくなり、平均的な品質も大幅にレベルアップしたことは、流通業者にとっても常に安心して扱うことができる商品になったことを意味し、消費者もまた、心おきなくチョイスでき、楽しんで飲めるということである。これは現代の商品が具備すべき基本要件ではないかと思う。
酒というものがこの世に生まれてから、随分と長い間、望んでもかなえられなかったことがやっと可能になったということである。これができたのも、やはり科学・技術の進歩に他ならない。
つぎに、これによって「昔あったおいしい酒」がなくなったという論は少々おかしい。 私どもは、酒づくりの長い歴史にも十分に関心をもっており、事実、平安時代や江戸時代の酒をそのまま復元したのでは、到底現代人が飲めるような酒にはならないことを、すでに私どもは体験ずみである。
よく言われる「昔はよかった」というのも、その昔とは一体いつの時代の、どんな酒をさしているのか、果してそのまま復元したものを飲んだことがあるのかなどを聞いてみたい。
現在の洗練された食生活になじんだ私どもが、あえて「昔」のようなつくり方をした酒を、「よりおいしく」感じるには、やはり最新の科学・技術を活用し、適確に現代風にアレンジする必要があることはいうまでもない。

「伝統は常につくりあげ、変えていくものであるはず」(石毛直道氏)
(2)このような新しい科学・技術の話をすると、きまって反論がくる。曰く「日本の酒づくりは伝統産業であり、情緒的な伝承技こそ本流だ」というのである。たしかに、「商品イメージ」としては「昔ながらの手づくり」などという言葉は好ましい。
しかし、人間が自ら手を下す工芸品などと違って、日本酒はあくまでも微生物が縦横に働いてつくる醸造物である。昔のままの手法をかたくなに守ろうと、最先端の科学・技術を駆使しようと、微生物の働きによって酒ができることには変わりない。また微生物の働き如何によってその酒質がきまることも、大昔から全く同じである。
二千年にも及ぶ酒づくりの歴史をひもとけば、「真の伝統」というものが、一体何であるかは次第にはっきりしてくる。
酒づくりは、その長い歴史の間、常に先人達の築き上げた伝承にとどまることなく、その時々に多くの人々の血のにじむような試行錯誤によって「革新」が繰り返され、次々と新しい技術が「創造」され、着実に進歩してきた。このように、時代と共に脱皮し変容していくことこそが「真の伝統」だということ、したがって「もっとも新しい方法」が「もっとも伝統的な酒」を生み出すことにもなるということを理解すべきであろう。
最近、地域性豊かな伝統的食文化も次第に失われる傾向にあるといって騒がれているが、食文化の大家といわれている民博の石毛直道館長の考え方はきわめて明解である。世界各地からあらゆる食材が入ってくる現代にあって「このようなもの(伝統食筆者注)を無理に残すのは、いかがなものでしょうか。保存が叫ばれるようになるのは、既に使命を終えたからです。実生活に意味を持たないものを残すのではなく、むしろ、伝統は常につくりあげ、変えていくものであるはずです」(注3)と喝破されている。酒文化を考える上でも、この言には耳を傾ける必要があろう。
注3:「21世紀への視座(79)石毛直道さんと考える」 (読売新聞夕刊3版7面、1999.1.19)

むしろ科学・技術によって広まる「多様性」
つぎに、科学・技術がめざす純粋化のために、「多様性」が失われたという論だが、以前は「懸命に精進したおかげで良い酒ができた」というような再現性のないつくり方が多かった。それが科学・技術の発展のおかげで、各微生物の本質まで解明することができるようになった。その結果、目的とするいろいろな種類の酒も、厳密に諸条件を設定して、きわめて再現性高く「意図した酒」につくることも可能となった。これによって、変化の激しい現在の市場が望むように、そのつど適応する商品を、いつでもつくりうる体制もできたといえる。むしろ、今後の方が、再現性ある「多様性」の時代になる可能性は大きいとさえ思われる。
(3)日本酒は、古代から神や祖霊をまつるため、一年を通じ、そのたびに「待ち酒」を醸造してきた。このため、四季の気候にあわせた醸造技術を次第に生み出すようになり、中世には、春酒、菩提、彼岸酒、新酒、間酒、寒前酒、正月酒などと、季節によって、つくり方も香味もそれぞれに違う酒を出現させていった。
それが江戸中期以降は、いろんな事情から「寒造り」が主力となり、それに対する技術だけが特異的に発達した。明治以降も「寒造り」が主流となって今日に至っている。しかし、歴史的にみれば、むしろ酒は四季を通じて醸造することこそ、日本酒本来の姿であるといえる。
三十数年前、私どもは業界の先陣を切って本格的四季醸造技術を開発、その体制を確立していった。最近になって、寒造り専門の杜氏・蔵人が全国的に極度に不足するという状況となったため、このシステムもようやく業界からも評価されるようになってきたにすぎない。本来、日本の酒づくりが持っている特質と、それに関連する技術の歩みをまずしっかりと認識してから、こうしたことも論ずべきであろう。

日本酒を「文化の酒」として生かすには
「技術の風土ばなれ」という論も、日本酒やビールについては少しおかしいように思われる。もともと、米や麦という貯蔵も移動も可能な穀物を原料とする醸造酒には、地域による水質の差異以外、本質的には風土性は少ないといえる。
たとえば、同じ醸造酒でありながら、ワインにヴィンテージがあるのに、なぜ日本酒にはないのかというのが世間の人々が抱く疑問だが、これは浅井昭吾氏自身の言を借りれば「ワインの場合はブドウのポテンシャルをいかに引き出すかが醸造の役割であって、醸造技術がワインをつくるのではない」という。たしかにそうである。これに対し、日本酒の場合は原料である米の性質よりも、むしろ各工程の技術如何が大きな影響を与え、微生物の挙動まで変えてしまう。このため、年ごとの地域の気候変化よりもそれをカバーする技術の方が品質に大きな影響を与えてきたという事実がある。したがって、日本酒はワインにくらべ、地域的な風土性は本来少ない酒で、本質的に「文明の酒」であるとも言える。
ただ、日本酒はその発生から今日まで二千数百年にわたって、日本というすばらしい風土文化の中で育ってきた。それだけに、今日のように科学・技術が大きく進歩し、情報が氾濫する中で、そうした文化をいかに生かすかを考えることも必要だ。とくに、本質的に「文明の酒」である日本酒を、「文化の酒」として脚光をあびるようにするには、日本酒のこうした特質を充分理解してはじめてできることなのである。



