 ▲昭和初期の月桂冠PR映画『選ばれた者』(1931年=昭和6年制作)より
▲昭和初期の月桂冠PR映画『選ばれた者』(1931年=昭和6年制作)より
清酒の文明化と文化性の再構築
酒造りへの科学技術導入、酒がもたらした文化的な価値
酒の産業を知る - 酒文化論・技術論
20世紀の酒文化を振り返り、酒がどのような価値をもたらしたか。「20世紀の酒文化」研究の一環として、酒文化研究所が行ったインタビュー。日本酒は地域的な風土性よりも、技術如何が品質に大きな影響を与えるため、本質的には「文明の酒」である。しかし、日本の歴史と文化の中で育まれてきただけに、日本酒の幅広い文化性を再構築すべきだと語る。
語り手:栗山一秀。1926年生まれ、月桂冠元副社長。
聞き手: 酒文化研究所・山田聡昭氏(インタビュー:1999年11月26日)
出典:酒文化研究所『月刊 酒文化』2000年3月号
外来の酒による酒文化の変貌
ー清酒にとって20世紀はどんな時代であったか、そして清酒がこの世紀にどのような価値を創り出してきたのかということについて、ご意見をうかがいたいと思います。
栗山
まず、酒の存在価値や価値観がこの20世紀という時代の中でどう変わったかということからお話しましょう。 私が酒の業界に入ったのは、ちょうどいまから50年前、20世紀の中間地点でした。当時、一次会で飲むのはあくまで日本酒が主流。戦前、すでに市民権を得ていたビールでさえ、二次会で飲むのが普通、ウィスキーは三次会になってやっとお目にかかるといった時代でした。
その後、ウィスキーのボトルキープが一世を風靡、寿司屋さんの棚にまで並ぶようになりました。しかし、これもようやく沈静化し、つぎに、焼酎ブームが起こった。それまで、焼酎はより大衆的な酒だとか、九州の地方酒だといわれていたものでした。昔から鹿児島では、常日頃は焼酎しか飲めなかったが、お祭と結婚式には必ず清酒が出てきたということでした。それがこの焼酎ブームによって、これまでのしきたりなんかに全くこだわりのない若い人たちに広まり、ついで都会の人々に普及するようになったのです。
大昔から日本では、米は農民にとっては食べるものでなく、汗水垂らして作り、税として献上すべきものだったのです。それだからこそ、米の酒・清酒はハレの飲みもの、非常なステイタスシンボルでした。ところがいまや、米が余って減反減反になる情勢で、「米の酒」の価値観も従来とは違ったものになったといえるでしょう。これも時代の流れの一つです。

-20世紀は平等と豊かさを目指した時代だから、酒にも従来の上下の構造を壊そうとする動きがあったということでしょうか?
栗山
そうともいえますが、むしろ流通経済の発達でいろいろなものが、大変なスピードで動くようになったことが要因でしょう。20世紀の大きな流れは、その前半において、人々があこがれる西欧の文化が日本にもどんどん入ってくるようになり、その「外来の酒」によって「日本の酒文化」も大きく変貌していく下地が形成され、それが、20世紀後半の戦後50年の間に、急速な変化としてあらわれてきたのだと思います。
とくに、最近のワインブームは「女性が気楽に飲める」というムード作りに成功したからだといえます。 これに似た現象は、すでに江戸期にもあったのです。江戸時代も中頃になると、上方(かみがた)から江戸に送られる酒が急激に増加し、その洗練された品質によって、当時の江戸の人々が抱いていた「上方にはとびっきりの上等がある」との思いや、「上方のすべての文物への憧れ」が「下り酒」によってますます強めていったのです。
そうした人々の想いは、明治になると、こんどは舶来文化へのあこがれに変わっていき、この時代の要請という流れはせき止められませんでした。
時代が要請した技術革新
-では、清酒にはどんな時代の要請があったとお考えですか。
栗山
たとえば、20世紀初め、日本につくられ始めたビール工場を酒造関係者たちが見学して驚いた。大変なカルチャーショックを受けたようです。
米と麦の違いこそあれ、同じ「穀物の酒」なのに、ビールは年中造られているではないか。しかもそれは、酒蔵全体を冷房する装置がその鍵を握っているらしいということを知った。酒造業を「近代化」させるためには、何としてもビールと同じように「四季醸造」を行う必要があるとの論が澎湃(ほうはい)として起こりました。これもまた無理からぬことだったと思います。
早速、和歌山の溝端久太郎という人などが私費を投じて試みていますが、当時の技術レベルでしかも単に酒蔵を冷房しただけでは無理だったのです。結局、時期尚早だったため、消えてしまいます。その後こうした技術レベルが上がるのに、60年もの月日がかかりました。
世紀後半、戦後の復興が軌道にのり始めた昭和30年代、日本の産業構造も大きく変容、それと共に、江戸時代以来酒の生産をになってきた季節労働の杜氏制度も、農漁村の過疎化、産業の地方進出などによって、その基盤をゆるがされ、杜氏・蔵人の数も次第に減少しはじめました。そこで当社は「いまこそ最新の技術を駆使し、社員による四季醸造体制を確立すべし」との決意を固め、業界の先陣を切って、そのシステムの開発にとりくみました。昭和36年(1961年)、ついに新技術によってこれを完成させ、その後さらに進歩を重ね、軌道にのせることに成功したのです。これこそ時代の要請にいち早く応えたものといえます。
21世紀に予想される変革とその対応を考えるとき、こうした実績こそ大きな示唆になるのではないでしょうか。
 ▲竣工当時の大手一号蔵。日本初の四季醸造システムを備えた酒蔵である(1961年)
▲竣工当時の大手一号蔵。日本初の四季醸造システムを備えた酒蔵である(1961年)
技術者との出会いと「防腐剤ナシ」の発売
-この世紀に、腐造が多くたいへんリスキーだった清酒造りが安定したものに変わり、産業化していきました。
栗山
全国的にみて本当に安定したと確信がもてたのは、20世紀も後半の昭和44年(1969年)からでしょうね。
-と言うのは?
栗山
業界をあげて、防腐剤としてのサリチル酸の全廃を達成できたからです。この時は、WHOの勧告やらマスコミ、世論などのはげしい要請に呼応しつつ、思いきって全国の蔵元一斉に防腐剤の使用を止めたのです。
ただ、当社はそれより60年も前、明治44年(1911年)、20世紀の前期にすでに「防腐剤ナシ」の商品を本格的に売り出しています。これは非常な冒険でした。そのころはまだ業界全体の技術レベルも低い時代でしたが、あえて発売にふみ切ったのは、「お客さんが安心して飲める酒にしなければならない」という、今でいう消費者志向の信念がすでにあったからだといえるでしょう。
サリチル酸による防腐については、明治12年(1879年)ごろ、東大に御雇教師として来ていたコルシェルトとアトキンソンとが論争、未解決のままサリチル酸を使えというコルシェルトの説を政府が採用し、日本酒の防腐剤として使い始めたものなのです。その後、明治36年(1903年)、内務省は飲食物へのサリチル酸使用を全面的に禁止したんですが、業界の強い要望もあって、酒への使用だけは大正3年(1914年)以来、無期延期にされたまま昭和44年(1969年)に至ったという経緯があったのです。
 ▲清酒メーカー初となった大倉酒造研究所、その初代技師として務めた濱崎秀
▲清酒メーカー初となった大倉酒造研究所、その初代技師として務めた濱崎秀
-月桂冠があえて業界にさきがけて「防腐剤ナシ」に踏み切った拠り所は、火入れをしっかりやればサリチル酸は不要というアトキンソンの説だったのでしょうか。
栗山
それだけではないのです。明治40年(1907年)、新進気鋭の大蔵省醸造試験所の鹿又技官が当社にひと冬滞在していろいろと実験するのを、11代当主・大倉恒吉は横で見ていました。当時、まだ珍しかった顕微鏡を使う。また、シャレーの蓋をはずして、しばらく置いておくと、シャレーには黴やら細菌やらいっぱいはえてくる。それらはすべて蒸し米や醪(もろみ)の上に落ちてくるということを知って、恒吉は大きなショックを受けたのだと思います。これを契機に、東大からはじめて技師を招聘、研究所を設立し、2年後にははやくも「防腐剤ナシの酒」を発売したのです。
しかし「防腐剤ナシ」の出荷では、ずいぶんと失敗もしています。東京に着いたらほとんど腐っていたケースさえあったというのです。当時、火落菌というのは何千種もあるということは学会でもまだわかっていませんでした。私が業界に入った50年前でさえ、学会での研究発表も、研究者それぞれが違う菌で実験をやっていました。だから、殺菌温度60度、5分でよいというのも、たまたまその研究に使った菌がその条件で死んだだけの話。私が学会に出る頃になったら「あなたの使ってるのはどんな菌か」くらいの質問がありましたが、当時はまだスライド写真がないから「黒板に絵を描きます」という程度(笑)。その後、乳酸菌研究の大家になられた京大の北原覚雄先生が膨大な数の火落菌の分類を完成され、それぞれの菌についての対策なども系統的にできるようになりました。
さらに10年ほど経って、昭和36年(1961年)、サリチル酸は飲食物に使っては駄目というWHOの勧告もでてきた。ついで昭和44年(1969年)、チクロ騒ぎと共に、清酒のサリチル酸も取り上げられたため、私共業界としても、さあたいへんなことになったのです。
 ▲月桂冠11代目当主・大倉恒吉。その一代で事業規模を100倍に拡大した(1912年=明治45年、北蔵構内の初代・大倉酒造研究所で撮影)
▲月桂冠11代目当主・大倉恒吉。その一代で事業規模を100倍に拡大した(1912年=明治45年、北蔵構内の初代・大倉酒造研究所で撮影)
酒は腐らないものという新常識
-醸造試験所はそれまで「サリチル酸ナシ」の技術指導はやっていなかったのですか。
栗山
明治38年(1950年)、大蔵省の醸造試験所が開設されて以来、「火落ち」については、随分と研究をつみ重ねてきたのですが、防腐剤を全くなしにするような指導はやってこなかったようです。しかし、私共はこうした世界の動きや政府の方針の流れをよみとり、杜氏たちの科学に対する認識が進んでいるのをみてとり、「もう全国の酒もサリチル酸なしにすべきだ。今ならやれるかもしれない」と思ったのです。
日本酒造組合中央会としても自主規制しようと決断するに至りました。しかし、いざやるとなると、たいへんなことでした。私共が明治44年(1911年)以来、苦労して独自に社内で開発してきた「防腐剤ナシ」の生産管理についてのノウハウを、業界のために公開せねばなりません。まず、詳細なマニュアルを作成、一番大事な菌学的清浄さとは何かということから、ホースの洗い方に至るまで、徹底的に細かいことを指示しました。これを、税務署と鑑定官を通じて全国の酒造メーカーに通達したのです。その結果、幸いなことに私共の心配したような火落ち事故は、全国的にもまったく起こらなかった。これは私共も予想外のことでとても驚いた。明治以後、醸造試験所の指導が大蔵省流酒づくり法を全国に押しつけたといろいろと批判されたこともあったようですが、そのおかげで杜氏さんの科学的知識は大巾にレベルアップしていたのです。この下地がなかったら、全国の酒を一斉に「サリチル酸ナシ」にはできなかった。これは、20世紀に日本酒業界がなしとげた大きなできごとの一つだと思っています。
-「科学の世紀」という、そのものですね。
栗山
この成功の背景には、もう一つ要因があったのです。当時すでに、全国どこの酒屋もタンクを始め、すべての道具が木製から金属やプラスチックに変わっていたことです。もしもまだ木桶などが残っていたら、いくら洗っても完全殺菌はできないため、こうした試みも成功しなかったはずです。丁度よいタイミングだったと思いますね。私なんか、子供の頃は酒は腐るもんだとおじいさんやお袋から聞いていました。それがこの一世紀で、酒は腐るものという概念がすっかり無くなり、いまや、消費者の皆さんも安心して飲める商品になったということです。今世紀最大の進歩だといえるでしょう。
 ▲大正時代の量り売り(はかりうり)
▲大正時代の量り売り(はかりうり)
元詰め商品が流通を変えた
栗山
もうひとつの大きな変革は、当社が「防腐剤ナシ」を発売した時、完全殺菌の必要から木製の四斗樽からガラス製のびん詰めに変えたことでしょう。これによってそれまでの流通体系もガラリと変わった。それまでは流通業者が樽から通い徳利に量り売りしていた。酒も醤油も味噌も小売屋さんが、お客さんに合わせて混ぜたりして、量り売りしていた。それを元詰めにしたのですから、ベテランの流通業者さんには大変失礼なことでした。しかし、このおかげで「防腐剤ナシの酒」を直接消費者に届けるシステムができたのです。
現在、私共の業界は、規制緩和などによって、かってない激変にぶつかっています。長期にわたる需要の低迷、3年後に迫った免許制度の自由化、熾烈化する他酒類との競争、急速な情報化の進展などの事態に際して、柔軟にしかもスピーディに対応していかねばなりません。
このように常に新しい目標に向かってチャレンジする姿勢を続けていく限り、21世紀への道は明るくひらけるものと私は信じています。
 ▲大正初期の木製看板。左は「口金付き」または「機械びん」とも呼ばれたびん詰。冠頭には「大倉壜詰部封證」の封緘に続け、防腐剤の入らない酒であることを示す「大阪市立衛生試験所検査之証」との証明印紙を貼り付けている。右は鉄道院(国有鉄道)の駅売り酒指定の第1号となった、実用新案登録の「コップ付き小びん」。ラベルに「防腐剤入ラズ」と記されている
▲大正初期の木製看板。左は「口金付き」または「機械びん」とも呼ばれたびん詰。冠頭には「大倉壜詰部封證」の封緘に続け、防腐剤の入らない酒であることを示す「大阪市立衛生試験所検査之証」との証明印紙を貼り付けている。右は鉄道院(国有鉄道)の駅売り酒指定の第1号となった、実用新案登録の「コップ付き小びん」。ラベルに「防腐剤入ラズ」と記されている
日本文化の輸出
-20世紀は酒が世界中を移動した時代でしたが、清酒の国際化をどうお考えですか?
栗山
最近、私共の「米国月桂冠」で「HAIKU(俳句)」というネーミングの高級酒を発売、なかなか好評なようです。企画したのはアメリカの若い女性です。俳句や酒の国際化もここまできたかと、驚いているほどです。10年前、われわれが、アメリカに酒蔵を造ったのは、それまで日本から輸出していたのでは、米の値段や、輸送費から、全く採算が合わなくなり、どうしても現地で造る必要が生じたからなのです。一年かけて調査、検討した結果、米の産地で水のよいサクラメントに進出することにしたのです。
これによって、はからずも日本文化をいろいろと紹介できるようになったのです。いまだに多くのアメリカ人にとって、日本はフジヤマ、ゲイシャ、サクラというイメージが多いのですが、それだけじゃないということを、この「俳句」という商品の普及によって、日本文化PRの一翼を担うこともできたと喜んでいます。
 ▲米国月桂冠が生産する代表的な商品群、右から2商品目が「HAIKU」(俳句)
▲米国月桂冠が生産する代表的な商品群、右から2商品目が「HAIKU」(俳句)
世界に通用する日本の「食」と「酒」
-外国人が清酒にトマトジュースを入れて「この方がうまい」と言うのを許せますか?
栗山
許せますよ(笑)。かって、私がカルチャーショックを受けたのは、豆腐にケチャップをジャーとかけ、スプーンでぐちゃぐちゃに潰して食べる。「これヘルシー」って(笑)。これなどは、「豆腐を使ったアメリカ料理」と言いたいけれど、アメリカの寿司なんかもこれと同じ、米の中にノリが巻いてあるカリフォルニアロールなどという手巻寿司にはびっくりしますね。しかし、異文化への入り口はそれでいいのだと思いますよ。
-日本にもいろいろな外国の食べ物や習慣が山ほど入っています。それに清酒が対応しきれなくなっている。日本料理と清酒の結び付きはものすごく強いですが、普段の食卓に伝統的な日本料理は並んでいません。
栗山
実際、日本でも若い人の家庭ほど国籍不明の料理が並んでいる(笑)。
-そこに入っていく清酒というのが、ものすごく大きいのではないですか。
栗山
たしかに、今は模索段階でしょう。日本の家庭の食卓は、将来、ますます無国籍化し、本当の日本料理は専門の料理屋に行かないと食べることができなくなるのかも知れません。しかし、最近、健康と長寿の面から、伝統的日本食は世界的にも断然すぐれていることが、いよいよはっきりしてきました。近い将来、必ずや日本の「食」と「酒」はもっと見直されてくると確信しています。では、日本料理の本質は何かということは、素材の香味を大切に、それをひきたてるように調理するという薄味の京料理を解析していけばわかると思いますね。これによって日本の酒の本質も垣間見えてくるように思います。
清酒の本質は「文明の酒」
-話が戻りますが、さきほど20世紀の清酒に「科学」が果たした役割が極めて大きいというお考えを頂戴しましたが、一方で清酒は「文化の酒」だという意見があります。
栗山
日本酒と言うのは「文化の酒」か「文明の酒」かという議論もありますが、本質的には「文明の酒」だと私は考えます。
もちろん、あらゆる酒は「文化の酒」として発祥する。しかし、ビールも日本酒も、ワインでさえも、いまや「文明の酒」になっていると私は思っています。だから、その「文明の酒」にいかに「文化性」を残していくかを考えないといけない。
それには、今後、技術と流通の変革をしっかりと見極めてゆく必要があります。現に、技術ではもう大きな変革が見えています。遺伝子工学です。日本は粒麹を使うからこういう酒になったとよくいわれるのですが、その影武者は麹菌の「グラB」という遺伝子であったということが、最近、当社の研究によって発見されたのです。こうした解析が進むと、これまで日本酒づくりの秘密といわれてきた本質もだんだん明らかになってきて、それに応じた的確な手が打てるわけです。
「文明の酒」というのは、見方を変えれば、再現性を高めた酒です。偶然ではなく、意図した酒がきちんと造れるということです。麻井宇介さん(酒文化研究家)なども、「現在の清酒はピュア、純粋さを追いかけた結果、均質な純林のようになってしまった。本来、酒はいろいろな雑多なものを取り込んだ自然林であって、純林にしていくのはいかがなものか…」との疑問を投げかけておられますが、これからは十分にコントロールできる技術があっての自然林だと私は思うのです。それにはまず純林を作る技術も必要です。ついで、それらを組み合わせ、上手に共生させてゆくべきだと考えています。
最近、若林三郎さん(醸造研究所・室長)から「20世紀最大の発明」と評価して頂いた当社の「液化仕込み」という技術も、今よりもさらに進展していくでしょうが、いい酒を造るための確実性の高い、21世紀へ向けての技術革新だと思っています。 21世紀の酒の技術は、さらに大きく飛躍し、これまで想像もしなかったようなきわめて魅力的な新商品が次々と生まれるものと確信しています。
 ▲大倉恒吉氏事業録
▲大倉恒吉氏事業録
「技術」を見る目を持つ経営
-最後に、御社にとって20世紀はどんな世紀でしたでしょうか。
栗山
月桂冠は、20世紀の初めは、まだ宿場町、港町の酒だった伏見の一地酒屋から脱皮しはじめた頃でした。19世紀から江戸送りの酒産地として大メーカーの多かった灘とはこの点が大きく違ったわけです。その後、数々の思いきった施策と涙ぐましい努力によって、ようやくこの100年の間にトップブランドになることができたのです。これには随分と時代を先駆ける技術革新があったのです。
まず、11代・恒吉が14歳で家業を継いだとき、お母さんに「あんたはまだ帳場に座ってはいけない。しばらく蔵の人と酒を造りなさい」といわれ、自ら酒を造る経験をしたことも結果的には大きな要因になったように思います。たとえば、貯蔵している酒が腐るということがいかに大変なことか、冬の間、酒づくりをしていた杜氏や蔵人たちが春になって帰ってしまった後で、数少ない店員たちだけで火入れを二度も三度もくり返すということは、汗水垂らして働いても、それは結果として値段を下げることにしかならないということを身に染みて知ったのです。もしも、初めから帳場に座っていたら金銭面のマイナスしかわからなかった筈です。同じ汗水流すのなら、腐らさないことにもっと努力すべきだというふうに考えたところが他のご主人たちと違っていたのです。また、後に採った数々の経営戦略もすべてがこうした考え方から始まっているのです。
当社が灘に進出したのもほぼ100年前。その時、はじめて播州杜氏を雇いました。それより2年前、伏見に2つ目の蔵を造った時も 越前杜氏ではなくはじめての丹波杜氏を雇っています。その頃、伏見の蔵はほとんどが越前杜氏で、新川の酒問屋から「越前と丹波は酒の造り方が違う」と聞いていたため、恒吉はそれがどう違うのかを知りたくて、丹波や播州など、越前とは違う流派の杜氏を雇ったのです。こうして明治30年代、すでに三流派の造り方を比較しながら醸造していた経営者は、全国的にみても恒吉だけだったと思いますね。
こうした考え方は恒吉自身が酒造りをやってきただけに、杜氏たちのやり方や、技術の違いに関心が生まれ、また理解することもできたのでしょう。
私は月桂冠では9人目の技師なんですが、11代・恒吉は私の入社した年の秋には亡くなったため、幸いにも最晩年の恒吉翁から屡々直接話を聞くことが出来ました。今も鮮明に憶えていますが、ひらめきの鋭い人だとつくづく感じました。その後の歴代社長も技術を重視し、品質第一主義の姿勢を貫いてきています。これはまた、現在、当社の基本理念の一つともなっている項目です。
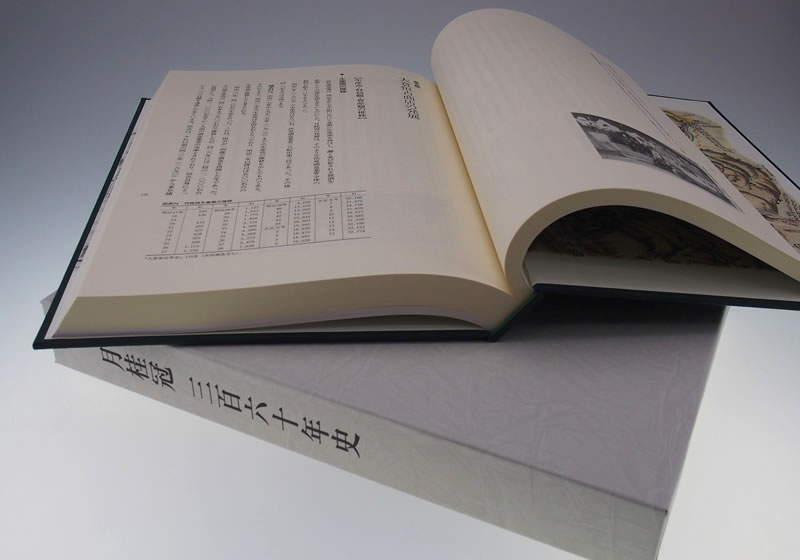 ▲『月桂冠三百六十年史』(1999年刊行)
▲『月桂冠三百六十年史』(1999年刊行)
-先に刊行された『月桂冠三百六十年史』からも何かヒントが得られましたか。
栗山
ええ。この社史の編纂委員代表も私なんですが、実は私が入社した時、すでに墨書された『大倉恒吉氏事業録』というのがありました。これは文字通り恒吉翁の事績だけを記したもので、300年の歴史を書いたものではありません。その後、昭和39年(1964年)、私自身が編集に当たった社員用のテキスト『月桂冠読本』の中で、「歴史編」を自分で書いてみて、古文書を調べる必要を痛感したんです。このため、あらためて本格的な社史を編纂するにあたって、まず古文書調査を専門の研究者に頼んだところ、5年もかかってしまいました。その後も遅れに遅れ、あしかけ10年もかかってしまいました。
それでも、20世紀の最後に刊行できたことを喜んでいます。考えてみれば、この10年の間に、私共の業界も随分と変化を重ね、業界全体としても業績の伸びない時期になっています。しかし、こんな時だからこそ、「社史」をひもとくことによって、足元を見つめ直すことがより必要になっているのではないかと考えています。
この『月桂冠三百六十年史』も内容の大半は、今世紀のことを中心に書く結果となりました。それほど業界としても、また、当社にとっても、激動の20世紀だったといえます。とにかくここに集大成された「伝統こそ創造と革新である」ということを再認識しながら、21世紀の新しい酒文化の確立に向かってしっかりと歩んでいきたいと思っています。



